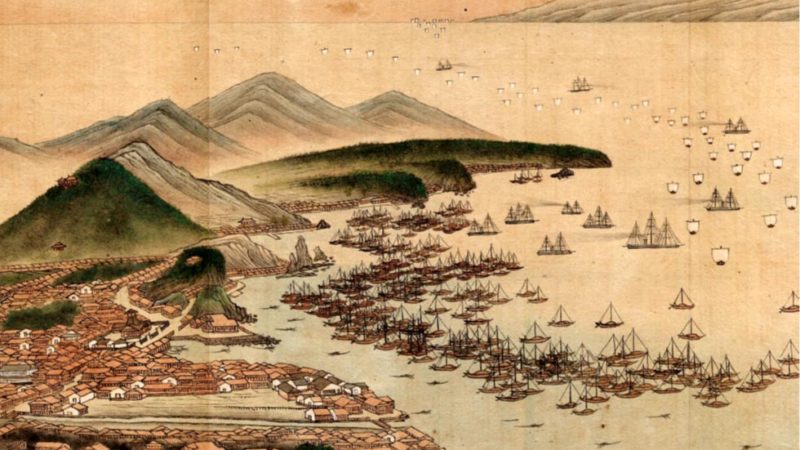北限のトチノキ
トチノキは東日本の森林(冷温帯林)に広く見られる樹木ですが、北海道では南西部だけに分布するため、道民にはややなじみの薄い植物かもしれません。しかし東北地方や中部地方では、栃の実は古くから食物や薬に用いられる貴重な森の恵みであり、木材としても幅広い用途があります。また、縄文時代の遺跡からはトチノキの実が頻繁に出土し、重要な食料資源だったことが分かっています。小樽の忍路土場遺跡では、トチノキなど木の実のあく抜きに使われたと考えられる水場の遺構も発見されています。

羽団扇のような5枚1組の葉が特徴。絵本「モチモチの木」のに登場する大木はトチノキ。
有用な樹木として、日本人には身近な存在であるトチノキですが、自生の北限はここ小樽だと考えられています。北海道の植生研究で著名な植物学者、舘脇操(たてわきみさお)らは「札幌国道の手稲と銭函の間が北限となっている」と具体的にその位置を述べています(日本森林植生図譜VII;1961)。現在も、銭函ICに近い銭函天狗山山麓や、桂岡の住宅地の奥、銭函川上流の森で北限のトチノキの姿を見ることができます。
小樽に生息する「本州的」な生物
小樽は、トチノキのような、北海道では限られた地域にしか生息しない温帯性の動植物が数多く見られる土地です。手宮公園の栗林で有名なクリ、長橋なえぼ公園や旭展望台でよく見かけるウワミズザクラ、天狗山の登山道に咲くナガハシスミレ、昆虫では日本の「国蝶」オオムラサキ、木の枝に擬態する奇妙な虫シラキトビナナフシなどがそうした例に当たります。このような「本州的」な生物の多産は、小樽の自然を特徴づけるキーワードの一つになっています。

小さな花がブラシ状に咲く。本州では若い花や実を塩漬けにして食用にする。北海道では小樽付近が北限とされる。

くちばし状に長く伸びた距(中に蜜を溜める花弁の一部分)が特徴。日本列島の主に日本海側に分布するが、北海道では道南以外ではきわめて少ない。天狗山に豊産。

東アジア南部を起源とする蝶で、北海道では限られた地域だけに生息する。小樽では1980年代に銭函で生息地が発見された。

木の枝に擬態することで知られるナナフシ類の中では、日本で最も北に分布する種類。しかし北海道での分布はきわめて局地的。小樽ではオタモイ地区の森に生息する。
小樽にすむ動植物がどのように小樽にたどり着き、定着したのか、わからないことも多いのですが、数万年の年月の中で、自然の中に起こった様々な出来事に影響を受け、現在の姿が形作られたことは確かです。逆に捉えれば、生物の分布には、地域の歴史に関わる膨大な情報が秘められていると言えます。複雑で豊かな小樽の自然はどのように育まれたのか、トチノキやオオムラサキの存在は、それらを紐解くヒントの一つと言えるかもしれません。